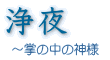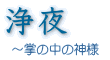ガーネット
毎年思うことだ。
どうして世の中には貧しいものと豊かなものの差があるのだろう。
この馬車は貴族街には回らない。だけど、そこで繰り広げられる今日の夜の光景は、回らなくても何となく想像がつく。
きっと貴族の子どもたちは今日をそんなに待ちわびていたわけじゃない。だって、彼らはいつでもどこでも、好きなものが手に入るのだ。望みさえすれば、たいていのことは叶うのだ。
何をもらっても、彼らにとってはいつもとたいして変わらない。
それは――自分の姿でもあった。
小さな袋をもらっただけで、飛び跳ねるようにして喜ぶ子どもたち。満面に笑みを浮かべて、いっぺんに春が来たみたいに明るく笑う人々。
笑いさざめく感情に満ちた篝火の広場に立って、ぐるりと辺りを見回しながら少女は思う。
豊かさって何なんだろう。貧しさって何だろう。幸せって、何なのだろう。
ぼうっとしているガーネットの肩を、御者の青年が揺らした。
「姫様、…もとい、お嬢様、そろそろ次の場所へ移動する時間であります」
堅苦しい言葉遣いが身に染み付いてしまっている青年は、ずれ落ちる仮面を何度もかけなおしながら少女を促した。
「うん…わかった」
凍てついた夜空に燃え立つ炎。火の粉を盛んに撒き散らし、惜しみなく周囲に熱と光をふりまく篝火に心を残しつつ、ガーネットは人々の輪を離れた。
|
|
二人
「馬車を停めて!」
ガーネットが突然声を上げた。
御者が慌てて手綱を引く。馬車は大きく軋んで急停車した。
「どうしたの?一体」
いぶかしむ母親に、少女は赤く上気した頬をさらに赤くして訴えた。
「路地の向こうの階段のところに、男の子がいたの。じっと座ってたの。あたし、見てくる!」
ぴょんと馬車から飛び降りて、夕方よりずっと深く降り積もった雪の中に少女は駆け出した。止める間もなかった。
母親はため息混じりに窓から顔を出して、御者に命じた。
「スタイナー、あの子を追いかけてちょうだい。車の入れない道になったら、降りて追いかけなさい」
「御意」
青年は馬車の向きを変えた。
ガーネットは目の端にちらりと映った少年を必死になって探していた。
この辺りは広場からも遠くて人気がない。しかももう夜更けだ。こんな時間にこんなところで階段に座り込んでいるなんて、よほどのことに違いない。
何かに導かれるように彼女は路地を駆け巡り、そして洗濯物干しの竿が縦横無尽に掛け渡された狭い路地の突き当りの階段に、探していた人物を見出した。
少年は頭からすっぽりと雪をかぶっていた。真っ白に塗りつぶされた頭の部分から、少しだけ明るい色の髪が覗いている。暗すぎてそれが何色なのかまでは分からない。顔もはっきりとは見えない。でも彼の体が固まっているように少しも動かないのは分かる。
雪の夜。いつもなら煌々とアレクサンドリアの町並みを遍く照らし出す二つの月も、薄い雲に覆い隠されてしまっていた。
ただ一面に敷き詰められた雪の明りのおかげで、辛うじてガーネットは少年を見つけ出すことができたのだった。
はあはあという荒い息遣いがジタンの耳を打つ。
長いこと一点を見つめて動かなかった目がようやく動いた。少しだけ。
目を上げた先に、真っ赤なほっぺたの、銀の仮面をつけた女の子がいた。
毛皮の縁取りの上等そうなコートを着て、自分を見下ろしている。
ジタンは興味を失って、膝の上の小さな生き物に目を落とした。
小さく身を縮め、丸くなって眠る子猫。
「寝てるの?」
女の子が尋ねる。
ジタンは首を振った。
「死んだ。…ずっと抱いて、あっためたけど、駄目だった。腹が減ってて、もう力が残ってなかったんだ」
痩せ細った子猫の頭を、ジタンはかじかんだ手でしきりに撫でた。
ガーネットは黙って少年の前に座り込み、赤いミトンを外して、子猫の体にそっと触れた。骨の上に皮を張ったみたいにごつごつとした感触。冷たくなった体に張りついた毛は信じられないくらい薄かった。
「親猫、いなかったのかな」
小さく、ガーネットは呟いた。
ジタンは頷く。
「うん。多分。ずっとここで待ってたけど、帰ってこなかったから」
少女はちょっとびっくりしたように目を瞬かせた。そうして、そっと手を伸ばすと、ジタンの膝から子猫を自分の膝の上に引き取り、外した赤いミトンでその体をくるんでやった。
「これじゃ、寒いかな」
独り言みたいな呟きを聞きとがめて、ジタンが首を振る。
「ずいぶん、あったかいと思う。俺――心が冷たいみたいで、手があったかくならなくて、だから一生懸命抱きしめてたんだけど…」
すっと少女がジタンの手を取った。少年の手より少しだけ小さな掌が、ふわりと彼の手を包み込む。
さっきまでミトンにくるまれていた少女の手は、湯たんぽみたいに温かかった。
「こうしてるとね、ちゃんとぬくもるよ。ちゃんと、温かい手にもどるよ」
慰めるように、一生懸命彼女は言った。
地表の照り返しだけが明かりの全てだった。辺りは薄闇に閉ざされて、何もかもぼんやりとしか見えない。例えばこの女の子の髪が、黒なのか栗色なのかも分からない。不意にジタンはそれがとても残念に思えた。
この小さな手の温もりを、ずっとずっと覚えておきたかった。
こんなに冷たく凍えるまで、この少年はここで子猫を抱きしめてあげていたんだ。そう思うとガーネットは胸が痛くなって、泣きそうになった。
「今夜は月が出てなくてよかったね。もし明るくて顔がはっきり見えてたら、精霊に連れて行かれてたかもしれない」
気を紛らわすように、努めて明るい声でガーネットは言った。
「精霊?」
「そう。それが今夜のお祭りなの。一年よい子にしていた子どもには、精霊が御褒美をくれるの。でも、顔を見せたら駄目なの。顔と名前を知らせるのは、精霊に連れて行ってくださいってお願いしてるのと同じことなんだって。精霊は、命を運ぶ使者でもあるんだって、お母さんが言ってた」
ジタンは何かを考えるように遠い目になった。
「だから、この子猫もちゃんと精霊に連れて行ってもらえるよ。最後まで側に人がいてくれて、寂しくなくて幸せだったと思う。――ほら、温かくなった」
ひとしきり喋った後、少女はジタンの手を離した。
ほかほかになった手を、ジタンはちょっと眺めて、それからそっとほっぺたにあてる。
「あったけえ」
「うん」
「あのな、掌には神様がいるんだって。心の温かい人間の掌には、あったかい神様が住んでるんだって」
照れくさそうに言って、それからジタンは小さな声でくっつけた。「親父が言ってた」
そこだけ小声になった理由をガーネットは知らない。知らなくてもよかった。彼女は素直に少年の言葉を受け入れて、びっくりしたように自分の手を見る。
「へえ――そうなんだ」
「俺の手、あっためてくれてありがとう。そいつ、俺がどこかに埋めてやるよ。貸して」
ミトンに包まれた子猫を受け取って、大事そうに胸に抱えると、少年は立ち上がった。
「じゃあ、俺、帰る。えっと、この手袋…」
「そのままその子に着せてあげてて。お願い」
「うん。わかった」
少年が、初めて笑った。仄暗い雪明りの中で、ちゃんと見えなくても、確かに分かった。
ガーネットも笑った。おかしいからじゃない。楽しかったからでもない。なんだかひどく――優しい気持ちになったから。
「さよなら」
ジタンが言った。そうして彼は雪の中を走り去った。
「さよなら…」
白いボタン雪が瞬く間に少年の姿を隠す。闇の向こうをじっと見つめて、しばらく少女はその場に佇んでいた。
|
|
ガーネット
「姫様!…いえ、お嬢様、こんなところにおられてはお風邪を召されますぞ!」
やっとガーネットを見つけ出した御者は、ぜいぜいと肩で息をしながら階段を駆け上ってきた。
「そ、その手はどうなさったのですか!?この寒い中むき出しとは…。さては曲者が姫様の手袋を盗んで行ったのですな!うむむ、許せん!今から私がとっつかまえて、ぎったんぎったんに」
「違うの」
早とちりの騎士を見上げてガーネットは首を振った。
「精霊が、私にもご褒美をくれたの。そのかわりに、手袋をあげたの」
「は?しかし、精霊とは…」
「ううん、きっと本当にいるんだと思う」
ガーネットは冷たくなってきた手に息を吐きかけた。そして、にっこり笑うと青年の手の中に小さなその手を滑り込ませた。
「うふふ、あったかいね、スタイナーの手。きっとスタイナーの手にも、神様が住んでるんだね」
「か、神様でありますか…」
何のことやらさっぱり分からない青年は、目を白黒させながら相槌を打つ。姫君は優しい瞳で彼を見上げて、うん、と頷いた。
「探してくれてありがとう、スタイナー」
そうして彼女は、まだ面食らっている青年の手を引いて、階段を下りて行った。
|
|
| |
ジタン
「どうした、こんな時間まで」
言うより早く拳骨が飛んでくる。
ごつんと頭のてっぺんにやられてジタンはちょっと顔をしかめた。
「う…」
見る見るうちに頭をもたげたたんこぶをさすりたいけれど、手が泥だらけで触れない。と、ボスが手拭を投げてよこしてくれた。
「埋めてやったのか」
素っ気無くボスが訊いた。
手にこびりついた泥を落としながら、ジタンはこくんと頷く。
「そうか」
言ってボスは暖炉の前の椅子を顎でしゃくった。
「あったまって寝ろよ。風邪なんかひくんじゃねえぞ」
後が困るからな、後が。
がははと笑って乱暴に言い放つと、ボスは隣のベッドルームに行ってしまった。
「うん。――ありがと」
ボスには聞こえないと分かっていて、ジタンはこっそり呟いた。
それから暖炉の前に膝を抱えて座る。
暖かな火が、冷たく凍った顔を照らした。その火はまるであの女の子みたいだった。
「神様…精霊…か」
いつしかジタンは夢の中に潜り込んでいた。
冷え切ってつかれきった体を横たえて、泥のように眠る。その小さな体を誰かが抱えてベッドに運んだ。
ボス。おれ、いい子じゃないのに、精霊からご褒美をもらったよ。
掌の神様にも会ったよ。
もごもごと寝言を繰り返す少年の髪を、大きな暖かい手が撫でる。
ああ。
ほら、今…神様がここにいるよ。
夢の中で、ジタンは笑った。
とても幸せな夢の中で。
|