広間に集う誰もが息をのんだ。
白い礼装に身を固めた細身の青年の優雅な挙動。彼に手を引かれてしずしずと広間の中央に歩みゆく、紫の髪の少女の美しさ。
楽団もしばし演奏を忘れ、彼らに見入ってしまう。やがてはっと我に返った指揮者の棒が、カチカチと譜面台を叩いて団員の目を覚ました。
そして彼らは最もシンプルなワルツを奏で始めた。その曲に乗って踊りだす二人の姿が際立つように。
「おい、ガーネット」
ジタンが傍らの女性をつっついた。
「え?」
「何をボーっと見とれてるんだよ」
そう言ってちょっとむくれている夫を見上げて、一瞬彼女は目を丸くする。
「ひょっとして、妬いてる?」
どことなく嬉しそうにガーネットはジタンの顔を覗きこんだ。
ジタンはほんの少し目元を染めて、慌てて
「ま、まさか。ただ、ほら、せっかく音楽が流れてんのに、踊らないのはもったいないと思ってさ」
言い訳をする。
「あら、いつも踊るのなんて面倒くさいっておっしゃってる方はどなたでしたっけ?」
「あれはだな、こういう夜会に出ると、淑女が寄ってきて困るからで、だな〜」
焦るジタンの腕にほっそりとした手を絡ませて、ガーネットはその肩に頭をもたせかけた。
「冗談よ。――見とれていたのは、一瞬クジャがあなたに見えたから。…やっぱり、よく似てる。ミコトとは髪の色といい、そっくりだと思ってたけど…仕草や立ち居振る舞いはクジャの方が似てるかもしれないわね」
「止めてくれよ!あんなへなちょこ野郎に似てるって言われたらちょっとショックだぞ」
「違うわ。あなたがクジャに似てるんじゃなく、クジャがあなたに似てるの」
まっすぐに自分の顔を見上げる視線に、ジタンは少しばかりばつが悪そうに唸る。
くすくすと声をたてて笑って、ガーネットは彼の手をとった。
「みんなとても素敵。クジャも、あなたも――それからエーコも」
歌うように呟くガーネットを、彼は眩しげに目を細めてみつめた。
そう言う彼女が一番美しいと言わんばかりの顔だった。
「踊りましょう?」
艱難辛苦が永遠には続かぬように、幸福もまた須臾の命であることを二人はよく知っている。だからこそ今この瞬間の幸福を心の底から味わおうとするのだ。そして、人々に降り注ぐ幸福を寿ぐのだ。
自分の腕にかけられたガーネットの小さな手を、ジタンはそっと握りなおす。
「ではお姫様、あなたをエスコートできます僥倖を賜れますでしょうか?」
芝居めかした口調に、ガーネットもわざとらしくちょこんと膝を折って、古式ゆかしいいらえを返す。
「ええ、喜んで」
こうして、広間に咲いた二輪の花は、長らくリンドブルムの語り草になったのだった。
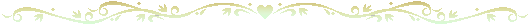
「帰るの?」
リンドブルムのお城のてっぺんに登って、エーコは自家製望遠鏡で国土を見渡しながら素っ気無く訊ねた。
傍らで両膝を組んで座るクジャは、気持ちよさそうに晴れ上がった青い空を見上げている。
「ああ。用事は3分の2、成就したからね」
「3分の2?あなたと、ミコトの結婚相手探しだったんでしょう?」
「それとエーコ嬢を元気付ける目的と。一応これが一番表向きの用事だったんだ」
「へえ、一応、ね。で、成就したのが」
「その表向きと、それから、あれかなあ」
クジャの見ている方向にエーコは望遠鏡を向けた。
下の展望台で、仲睦まじく語り合う二人がいる。金色の髪を風になびかせて、台座に設えられた固定望遠鏡を覗く少女。彼女の耳元で、おそらくはその土地の説明をしてあげているのだろう青年。長い黒髪を細い紐で結わえて背中に垂らしている。引き締まった長身で、体つきから察するに護衛官か何かなのだろう。
「シャノンっていう、ジタンの子飼いの部下らしいんだ」
気がつくといつの間にかクジャがエーコのすぐ横に立っていた。
「ってことは、つまるところ、あなただけアウトだったんだ」
「だね」
「ご愁傷様」
エーコが表情を緩める。ふっと見せたその少女らしい優しい瞳の色に気づいて、すかさずクジャが立て板に水とばかりにまくしたてる。
「あ、ちょっと同情してくれた?んじゃ、可哀想なボクの相手になってくれるとか。そうすると、願いは全部かなうんだけど。それにほら、夜会の時の僕らって、結構評判よかったしさ」
ゴキッ。
だが毎度のことながら、彼の願望は天誅の一撃で終焉を迎えたのだった。文字通り、望遠鏡の鉄槌である。
「ボクってほんとーに女性に恵まれない運命なんだよなあ」
頭のてっぺんのたんこぶをさすりながら、なみだ目でクジャがぼやく。
「いいじゃない。こんな最高のレディのダンス初体験をあげたんだから。それだけで人生の女性運全部とつりあうくらいの幸運だわよ」
「じゃあやっぱりボクの女性運はたいしたことないってことじゃないか」
しゃがみこんで小声で文句をたれるクジャ。耳ざとく聞きつけたエーコが目を光らせて振り返る。
「何か言った!?」
「いいえっ!なんにもっ!」
ばびゅん!という音さえ立てそうなくらいの勢いで、クジャは屋根の端にとびのいた。
その姿がよほどおかしかったのか、エーコが声を上げて笑う。
胸のすくような青空とおなじくらい、すっきりした明るい声で。
そのとき、眼下から彼を呼ぶシドの声が響いた。
船の出る時間だと、その声は告げた。
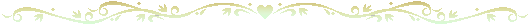
山並みからリンドブルムの艦隊が威容をあらわした。
クジャたちを黒魔導士の村に送り出すためだけのセレモニーである。それほどエーコが元気になったのが嬉しいのだ。その一助となってくれた彼らに、感謝の意を表したかったのである。もっともそこには自分の手作り飛空艇を見せびらかしたいシドの趣味もちょっぴり混じってはいたが。
エーコはポートには見送りに下りなかった。ずっと屋根の上に居座ったまま、じっと空を睨んでいた。
数隻の飛空艇が城に影を落とし、ゆっくりと北へ渡って行くのが目に入った途端、彼女はすっくと立ち上がった。
「クジャ!」
力いっぱい手を振って、大声で叫ぶ。
飛空艇のエンジン音にかき消されるのは承知のうえである。それでも彼女はここで最後まで見送りたかった。たとえ彼が気づかなくても。
だが、彼女の予測とは裏腹に、甲板に佇んでいた銀色の髪の青年は、眼下で手をふる少女にしっかりと気がついた。身を乗り出して、彼もまた手を振って応える。
エーコにもその姿は見えた。
「クジャ、あのね」
強い風に長く伸びた髪をなびかせながら、エーコは声の限りに叫んだ。
「あたし、あんたのこと嫌いじゃないわ!お嫁さんにはなれないけど、――嫌いじゃなかったわ!」
遥か下方を見つめる青年は、自分の耳を疑うように、ニ、三度瞬きをした。
固まること数秒。
それからようやく、少女の言葉が腑に落ちてきたらしい。にっこりと…このうえなく嬉しそうに、やさしく微笑んだ。
彼が何か叫び返したが、その声はエーコには残念ながら聞こえなかった。
それでも彼が微笑んだのが、そして自分の声が彼には届いたのが、エーコにははっきりわかった。
リンドブルムの国旗をはためかせ、旗艦は腹を見せて大きく旋回する。
その後に数隻の船が続き、そうして一隻だけが帰途へ向かって外れていった。
遠ざかってゆくその船の姿が完全に青空の向こうに消えるまで、エーコは手を振り続けていた。
遥か彼の地まで、その深き想いが届くように。