|
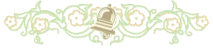
A bell rings on the hill.
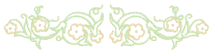
<4>
アレクサンドリア巡回の行程は、全部で五日間だ。中二日で一日の休みが入る。
二日目の日程を終えて、ガーネットは一旦アレクサンドリア城に戻ってきていた。陸路ではなく大船団を組んでの空路を使うようになってから、こういう芸当もできるようになったのだ。
「資料の整理がとにかく楽になりましたわい」
シェダ宰相はよくそう評した。
ガーネットとしても、城に帰って来れるのは嬉しい。そこは彼女が一番気を抜ける場所だったから。
宰相にゆっくりと休養するように告げて、女王陛下は一人で執務室に向かった。
部屋に入った途端、彼女は空気が流れているのに気付いた。
風?
職務用の卓が置いてある部屋の窓は閉まっている。隣の休憩用の小部屋から風が吹き込んできているらしい。
ガーネットはそっとその部屋を覗いた。
もしかしたら賊かもしれない。でも、もしかしたら――。
白いレースのカーテンが、淡い秋の真昼の光をはらんで揺れていた。
バルコニーのガラス戸が開け放たれている。
もしかしたら。
窓際の、暗く影を落とした壁に寄りかかっている人影がゆらりと動いた。
そしてその人影は、大きく開いた窓からいっぱいに注ぐ光と風の中に立った。光に縁取られた彼の金色の髪が風にそよぎながらきらきらと光っている。
胸がいっぱいになって、ガーネットは口が聞けなかった。
「おかえり――なさい」
かろうじてそれだけ喉の奥から搾り出す。
エーコは約束を守ってくれたのだ。こうして、ジタンをここに呼び戻してくれた。真っ先に彼女はそう思った。
ジタンはゆっくりと彼女に近づき、そしてその目の前に跪いた。
いつもの彼の姿だった。簡素な役者風の服と、腰に佩いたオリハルコン。ぼさぼさの髪。
それはちっとも貴族らしくはなくて――。でも。
「王女様。今からわたくしめがあなた様を誘拐させていただきます」
言って彼は顔を上げた。そうしてにかっと笑った。彼女のよく知っている、あの笑顔で。
「だけど今度は一生――ずっと誘拐し続ける。途中で手放したりしない」
自分の前に片膝をついて座り、自分の手をとって自分を見つめている青年の姿が、見る間に歪んだ。そしてすぐにそれは全く見えなくなってしまった。代わりに閉じた目からぽろぽろと涙が零れ落ちる。
「はい」
泣きながら、懸命にガーネットは肯いた。
「そうしてください。ずっと、ずっとわたくしをさらったまま、あなたのもとに置いてください」
「え?――いいの?」
拍子抜けしたような情けない声をジタンは思わず上げてしまった。それくらい意外な返答だったのだ。彼は玉砕覚悟だったのだから。
「もちろんです」
頬を伝う涙を手の甲でこすりながらガーネットは不思議そうにジタンを見つめる。
「これって、その、プロポーズのつもりなんだけど」
頭をぽりぽりかきながらジタンはうろたえて立ち上がる。
「わかってます!」
「ホントに?」
「ジタン…私が信じられないの?」
視線は真正面からぶつかる。ガーネットの真剣な眼差しが、そのいらえの確かさを証明していた。
「いや、なんですぐに気が変わったのかなって…」
「変わってなんかないわ」
「え?でも」
「あの時だって私は別に断ったつもりじゃなくて…ただ、わたし…私が結婚したいのは、貴族のあなたでも盗賊のあなたでもなくて、ジタン・トライバル自身だったんだもの。あのときの貴方はまるでどこから見ても本当に立派な貴族みたいで…」
「いつもの俺と別人だった?」
こくんと肯くガーネット。
「失礼だな」
「私のわがままだと分かっているのだけど、でも私は私のよく知っている、私のジタンの口から、その言葉が聞きたかったの。私は…”あなた”のものになりたかったの」
.その言葉を聞いた途端、弾かれたように――ジタンは彼女を抱きしめていた。強く。優しく。想いをこめて。
「絶対、離さない」
絹のように艶やかで豊かな黒髪に顔を埋めて、ジタンは囁いた。
「うん」
こくんと、黒髪が肯く。
「ずっと一緒に生きていこう?」
「はい」
「ずっと」
――ずっと。
固く抱き合った二人の姿を風に運ばれた秋の光が照らし出す。
バルコニーに張り出した梢にさえずる小鳥の音の向こうから 遠く正午を告げる鐘の音が鳴り響く。
それは湖を渡り、高く連なる山肌に木霊して地に満ちた。
アレクサンドリア中の教会の鐘の音は、やがて時を告げる代わりに女王のご成婚を告げるだろう。
新しい門出を寿ぐために。
新しい伝説の始まりを謳うように。
|