|
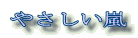
アレクサンドリアの位置する高緯度地方では、この季節になると必ず一度は大きな嵐が吹き荒れる。
その日は朝から雲行きが怪しかった。
ジタンが出かけたまま帰ってきていないので、ガーネットはなんだか落ち着かない。
まず間違いなく嵐がやってきそうだった。その嵐に巻かれて、ジタンにもしものことがあったらどうしよう、と、胸が騒いで仕様がなかったのだ。
いつも彼の行く先はしれなくて、そしてもっぱら彼の移動手段は自分で手に入れた小さな飛空艇だった。飛空艇は、上空の悪天候に弱い。ガーネットの心配もあながち的外れなものではなかった。
王が日中政務をこなす王の間は、王宮の奥まった位置にあった。
いつもなら、採光のために天蓋にはめ込まれた大きなステンドグラスから、七色に彩られた美しい光のカーテンが広間に降り注ぐ。
が、今日はうす曇りのせいか、部屋の隅に立てられた燭台の灯りがなければ、手元にある書面すら読みづらかった。
天候を読み取る手段はその天窓しかなく、そして分厚い天窓は詳しい様子は教えてくれない。だから嵐が来るかもしれない心配はしても、実際に外がどんな様子なのかガーネットが知ることができるのは、政務が終わる午後でしかなかった。つまり、午前中の間ずうっと、彼女はジタンの心配をし続けていなければならなかったということだ。
やっと仕事から解放されて自分の部屋に戻ったガーネットは、ガタガタと大きな音をさせて揺れる窓を見て、さらに不安を募らせた。
まだジタンは帰ってきていない。
彼は自分に充てられた部屋を丁寧に辞して、ガーネットの私室を自分の住処と決めていた。
その部屋は、がらんとしたままだ。
待ってる者の身になって欲しいわ。
ベッドの端に腰を下ろしてふかふかの枕を抱き締め、その中に口元を埋めて愚痴をこぼす。
いつ日が落ちたのか分からぬまま、気がつくと侍女が灯明を点しに各部屋を回る足音が響き始めた。
女王の私室にも明かりが入る。
ありがとう、という女王のねぎらいの一言に、恐縮のあまり身を縮めて退出する侍女の姿が廊下の端に消えてしまってから、ガーネットは大きな溜め息をひとつ、ついた。
こんな落胆の色の甚だしい溜め息は、誰にも聞かせることなどできなかった。
聞いた途端、まず間違いなく、王宮中が大騒ぎになってしまう。女王がお加減が悪いらしい、とか、もしかすると何かお悩みがあるのでは、とか、いらぬ推測が飛散するのは目に見えていた。
だから彼女はまたもや枕を抱えて、誰もいなくなってから溜め息を吐き出すのだ。
が。
吐き出し終えてしまう前に、彼女の前に人影が立った。
え?
顔を上げると、目の前の人物は、濡れそぼった金髪から雫を垂らしながら、体を屈めて彼女の頬にキスをした。
「ただいま」
物思いに耽っていたせいか、彼の気配に全く気付かなかったガーネットは、不意をうたれてびっくりするばかり。ただでさえ大きな眼をもっと大きく見開いて、そして次の瞬間、びしょ濡れの彼の体に抱きついていた。
「ジタン!ジタン!心配したのよ!」
彼の首に腕を巻きつけて離そうとはしないか細い力に、ジタンはちょっと途惑いながらも抱き締め返す。
「なんだか、今夜はいつにもまして熱いお出迎えなんだな。…嬉しいけど」
いつものからかうような口調。
ガーネットは安心すると同時に、はっと、彼が濡れ鼠であることに気付いた。
「ごめんなさい、私…」
慌てて乾いた布を取り出してきて、彼の体を拭こうとする。
「ああ、大丈夫だ。自分で拭くよ」
その布を取り上げて、だがジタンは、まずガーネットの顔とドレスについた水滴を拭った。
「びしょぬれの俺なんかに抱きつくから、お前まで濡れちゃったじゃないか。って、まあ、それを抱き締める俺も俺だけど」
「私はいいわ。あなたの方がカゼをひいちゃう」
体を引こうとするガーネットの腰に手を回して、それ以上離れないようにしながら、ジタンは片目をつぶって見せた。
「ちょっとじっとしてろって。じゃないと、変なところ触っちまうだろ?」
「へっ、変って…」
ガーネットはかっと頬を赤く染める。
その彼女の反応がさも楽しくてならぬように、ジタンは小さく声を立てて笑った。
「ジタン!!!」
からかわれているのが分かって、さらに顔を赤くしながらガーネットが可愛らしい拳を振り上げる。
その拳を軽く掴んで、自分の唇に引き寄せ。
「よし、これで拭き終わり」
それからジタンは、ぽん、とガーネットの頭のてっぺんを軽く叩いた。
「もう、ジタンったら」
既に何千回呟いたか知れぬフレーズである。
だがそれを呟く方も、聞かされる方も、一向に飽きた風もなく、むしろ嬉しそうに笑みを交し合うのだ。
もし傍で見ているものがいたなら、呆れて物も言えなかったろう。
だが幸いなことに、この部屋には彼ら以外誰もいない。当たり前のことだが。
窓辺に置かれた蝋燭の炎が、隙間風に揺れている。
硝子を揺らす風の音は激しさを増すばかりである。
「今夜は荒れそうだな」
カーテンを開けて外をうかがっていたジタンが、後ろのガーネットを振り返りながら言った。
「雨もひどくなってきたみたい。よかったわ、本当に。あなたが無事に帰ってきてくれて」
ガーネットはそっとジタンの腕に手を触れた。そこにいることを、もう一度確認するように。
「俺が無事じゃないことなんてないさ。今までだって必ず君の元に帰って来ただろ?」
「だって、先のことは誰にも分からないもの。それに飛空艇は危険だし…」
ゆらめく琥珀色の光の中で、ジタンは彼女を引き寄せる。
「心配性だよな、ダガーは。でも、もう俺も帰り着いたし。安心してお休み」
耳元で優しく囁く彼の吐息がくすぐったくて、ガーネットは軽く首をすくめた。
「ええ。そうね…」
旅から帰ったばかりで、きっとジタンも疲れているに違いない。
ガーネットはそう思った。
もっと一緒にいたいのはやまやまだったが、ここはジタンを休ませてあげることが一番だと。
夜が更けてゆくに連れて、雨風がひどくなっていく。
夜半には、とうとう雷まで鳴り出した。
かなり近いところに落ちているらしい。
凄まじい稲光のすぐ後に、轟音が鳴り響く。
さすがのジタンも浅い眠りから覚まされて、ソファの上に半身を起こした。
ぴかっ!どおぉぉぉん。
雷の落ち方と来たら、尋常ではない。
部屋全体を揺るがすような衝撃に、ふとジタンは隣室に眼をやった。
暗く、明かりを落としてしまっている部屋で、ガーネットは眠っている筈だった。
が、こうして自分すら起こされてしまったほどの雷である。
ガーネットは大丈夫だろうか?
子供ではないのだから、とも思ったが、もしかしたら寝つけないでいるかもしれない。
眠っていればそれに越したことはない。寝顔を拝みにゆくつもりで、ちょっと覗いてみるか――。ジタンはそっとソファから立ち上がった。
真っ暗な部屋。
彼が一歩中に足を踏み入れた瞬間、部屋全体を閃光が覆った。
どごぉおお!
という大音響と、誰かが彼に抱きついてくるのとがほぼ同時だった。
閃光が消えた直後の室内では、さしものジタンも眼が利かない。だがその柔らかな感触と、つややかな髪のかぐわしい香りで、抱きついてきたのが誰かはすぐに分かった。
「ダガー。大丈夫か?」
小刻みに震えながら、ガーネットは彼にかじりついている。
「だ、大丈夫、ただ、ちょっと、びっくりしただけなの」
ジタンの腕に包まれているうちに、ようやく落ち着いたらしい彼女は、ほう、と息をつきながら、そう応えた。
「そうか。じゃあ、俺、寝るわ」
踵を返そうとするジタンのシャツの裾が、何かに引っ掛かったように伸びる。
ガーネットがしっかりとその裾を掴んで離さなかったのだ。
「あ、あのね、もうちょっと――きゃああ!!!」
彼女の言葉を遮るようにまたもや強烈な稲光が走った。と同時にたまらずジタンにしがみつく。
ジタンの笑顔は、生憎誰にも見られることはなかった。この上なく嬉しそうな、そして優しい笑みだったのだが。
ガーネットは。
ついさっきまで、一人で寝室で震えていた。
本当は怖くて怖くて、すぐにも隣の部屋のジタンのところに飛んで行きたかった。
だが、彼は長旅から帰ったばかりで、ひどく疲れているように見えた。
雨に打たれてびしょぬれになった姿のせいで余計にそう思えたのかもしれないが。
それにしても、ぐっすり寝ているはずの彼を起こすのは忍びなかった。
こんなことで。
と思う上から大音響が降ってきて。
とてもじゃないけれど一人でベッドにいることができなくて、せめてほんの少しでもジタンの近くにいようと、彼女は執務室の入口まで壁伝いにやってきていたのだった。
そこに、逞しい腕が差し伸べられたのだ。
思わず彼女はその腕にすがりついた。
人肌の優しい温もりが、彼女の剥き出しになった白い腕に触れた。
その瞬間、それまでの恐怖が、嘘のように霧散した。
ジタンは自分の胸にしがみ付く女王様の肩とひかがみに腕を回し、ひょいと軽く抱き上げた。
文字通りお姫様だっこで、そのまま彼女をベッドに横たえる。
彼の首に回したまま離そうとしない彼女の白い細い手を、彼がそっとはずす。
それから、徐に自分も彼女の傍らに横になった。
「眠るまで、ここにいてやるよ」
「ジタン…」
二、三度瞬いて、ガーネットはこくんと頷いて。
それから安心したように、ジタンに身を摺り寄せた。
彼女の全てが彼の中にすっぽりとはまってしまう。
そんな華奢な体を優しく抱き締めながら、ジタンは胸の内で嘆息する。
この状態はきついよなあ。
こよなく愛しい女性は、今寝間の薄着一枚しか身にまとっていない。
その薄布越しに抱き締めているのだ。素肌が密着しているに等しい感触が、彼の全身を刺激している。
これで欲情しない男は絶対にいない!と、ジタンは断言できる。
だが、彼はきちんと手順を踏み終えるまで、彼女を勝手に自分のものにはしないと心に決めていたので。
本当はその薔薇色のふっくらとした唇を味わいたかったのだけれど、でもここで一歩を踏み出してしまったら、怒涛のように突き進んで、自分で自分が制御できなくなるのは目に見えていた。
だから。
かなり精神力を要求される展開ではあったが、これも修行の内と自分に言い聞かせ、ひたすら紳士たるべく不屈の努力を続けたのだ。
その恋人の心中など預かり知らぬ平和な女王様は、本当に安らかな心を抱いて、心地よい微睡に身を浸す。
外がどんな嵐でも、どんなにひどい雷が鳴っても、この人の腕に包まれているだけで、どうしてこんなにもほっとするのだろう。
その絶対的な安心感の中にたゆたいながら、やがて彼女は小さな寝息を立て始めた。
腕の中の温もりが眠りに落ちたのを確認して、ジタンも欠伸を洩らす。
それからもはや動くのも億劫な様子で、そのまま彼女の匂いに包まれて、彼もまた深い眠りに誘われたのだった。
|