|
シドのたっての望みで、リンドブルム大公一家は毎朝小さな食卓で肩を寄せ合うようにして朝食を摂る。その日も、彼らはいつものように一家団欒を楽しんでいた。
「エーコ、もう具合は大丈夫なの?」
なぜかこのニ、三日エーコは珍しく体調を崩していた。
娘の額に手を当て、顔を覗きこむヒルダにエーコはにっこり笑ってみせる。
「うん、おかあさん。心配しないで」
本当は、別に熱が出たわけでもなんでもない。ちょっと複雑な気分になっていて、ジタンとガーネットに会いたくなかっただけだ。
黒魔導士の村に毎年ビビを偲んで集まることは彼らの中では周知の事実である。当然シドもヒルダも知っている。だから今年も彼らは愛娘がその地に赴くものと信じて疑わなかった。もし行かないなんて言ったら、シドは「それは薄情と言うものだ」と説教を始めるだろうし、ヒルダは落胆のため息をつくだろう。エーコはそれだけは避けたかった。二人をがっかりさせたくなかったのだ。
でも、ジタンたちには会いたくなかった。だから仮病を使ったのである。
「もうすっかりいいの。でね、できるなら来週でも、ひとりで黒魔導士の村に行きたいのだけど…。ビビに会いたいもの」
言いにくそうに上目遣いで懇願するエーコを、ヒルダは抱きしめる。
「エーコ!あなたはなんて優しくていい子なの!」
シドもご満悦の表情で嬉しそうに肯き、その通りだと賛同しようと口を開いた。
「本当に…」
「さすがエーコちゃんだね!」
不意に、小ぢんまりした団欒の部屋にテンションの高い声が鳴り響いた。
一同はぎょっとして入り口を振り返る。
「げえええっ!」
「あら」
「な、なんと!」
三者三様の叫びを上げて、三人は硬直した。
貞操帯まがいの衣装に唐草模様の風呂敷を背負った不審な男が、戸口に立っていたのだ。額に手を当て苦悩に沈む美少女を背後に従えて。
彼は感動に満ち満ちた表情で両手を広げ、ずかずかと食卓に近寄るとまずシドの手をしっかと握ってぶんぶん振った。
「お久しぶりです、お父さん!」
「おとう…??」
事態が飲み込めないシドは茫然自失の体で固まっている。
そんなことにまったく頓着せず、男はすぐにその横のヒルダの手をとった。
「お久しぶりです!おかあさん!以前は失礼なことを致して済みませんでした。でもご安心ください、今後はエーコお嬢さんを大切にして共に生きていきます!それが僕のせめてもの罪滅ぼしでっ」
ぼたぼたぼた…。
黙らせようと背後から椅子を振り上げて迫るミコトの目の前で、クジャは頭からスープをぶっ掛けられた。
ぶっ掛けた相手がエーコ嬢であることは言うまでもない。
「なんであんたがここにいるのよ!そいでもって何であたしがあんたと共に生きていかなきゃいけないのよ!加えてあたしのお父さんとお母さんを、勝手にお父さんお母さん呼ばわりしないでくれる!?二人はあたしのものなの!誰にもわたさないんだから!」
腰に手を当てて、仁王立ちになりながら前かがみで怒るその姿は、6年前とちっとも変わっていない。…いや、身長は伸びたし、面差しにも少女らしさが滲んではいるが。
「エーコ〜」
愛娘の怒りの矛先は微妙にピントがずれているのだが、感極まった養父母にとってはそんなことは関係ない。ひたすら自分たちを「わたしのもの」だと言ってくれたことが嬉しくて、二人手を取り合い、ナミダにくれている。
「そうやって怒る姿も麗しい…。僕の目に狂いはなかったよ。この世界で一番美しい女性に成長するのは君に違いないって、かねてから思っていたんだ」
長いまつげをぱちぱちと瞬かせ、両手を広げてクジャはノタマう。
まったく状況がわかっていないにもかかわらず喜びに咽ぶ養父母も養父母だが、その二人の姿が全然目に入っていないこの男もたいしたものである。
「そんなこといつ言ってましたっけ?」
後ろから投げつけられる冷たい妹の突っ込みにも動じることなく、彼はエーコの目の前に跪いて彼女の小さな手をとった。
「な、何すんのよ!」
顔を真っ赤にしてエーコは急いで手を引っ込める。
あえてそれをとどめようともせず、クジャは少女を見上げてにっこりと笑った。
「自分が守ると決めたレディに対して、騎士たるものはこうして礼を尽くすのだと聞いたことがあるんだけど?」
どことなくジタンを偲ばせるその面を、エーコは仏頂面で睨みつける。
そうよ、…あんたを助けに行く時、ジタンがガーネットにしてたわよ――と、喉元まででかかった言葉を彼女は慌てて飲み込んだ。それを口にしてしまうと、自分が惨めになりそうな気がしたのだ。
あのときジタンがガーネットに何を言ったのか、飛空艇の甲板からは知るよしもない。ただ遠目に見ても伝わってきたのは、地上の二人が分かちがたい絆で結ばれているのだと言うことと、その間に自分は入っていけないのだと言うことだけ。
あの頃の自分はまだまだ幼い子どもだった。だけど胸がひりつくような気持ちははっきりと覚えているし、今もまた同じ気持ちを味わっている。
だからどことなくジタンを思わせるクジャの表情が、なおさらエーコには痛かった。
跪いて欲しいのは一人だけなのに、その人はつい先月盛大な式と共に人のものになってしまったのだから。
「誰が騎士よ、誰が」
「ボク」
「騎士はそんな猥褻物みたいな格好はしてない」
ズバリと杭を脳天に打ち込むような物言いだが、当のクジャは平気である。
「うーん、エーコちゃんはまだ子どもだからそう思うかもしれないねえ。でも見る人が見たら、僕のこの姿の高踏的孤高の美しさが解る筈なんだ。ボクの美しさを世界に供するために、ボクはあえてこういう格好をしているんだよ。万民のためにわが身を削る。滅私奉公則天去私!これぞ騎士道精神の最たるものじゃないかい?」
が、クジャお得意の煙に巻き攻撃も、傍若無人唯我独尊少女エーコの前では通用しないようだ。半眼開きで腰に手を当て、仁王立ちしたままの格好でエーコは横柄に胸をそらした。
「ご高説はうんざりなのよね。で、要するにあんたは何でここに来たのよ」
本来の目的の一つを思い出して、クジャははっと我に返る。
「ああ、そうだ、これ」
視線をずらしてぶすっと黙り込んだエーコの目の前に、クジャは背負っていた唐草模様の風呂敷を差し出した。
「何よ、これ」
「あけてごらんよ」
言うことを聞くのは癪に障るが、好奇心が疼いてたまらなかった彼女はすぐにその包みを開く。
「あ」
出てきたのはビビが愛用していた魔導士の杖。
彼が息を引き取る時、枕元にエーコが置いた杖だった。
「さすがに帽子は持ってこられなかったから、代わりにこれを…ね。きっと、エーコちゃんはビビに会えなくて胸を痛めてるだろうと思って」
「い、痛めてなんかないのだわ」
つん、とそっぽを向いてエーコは憎まれ口を叩く。だが、その手には杖がしっかりと…大事そうに握られていた。
「体はもう大丈夫なの?」
ミコトが横合いから尋ねる。
「うん、もう大丈夫」
こましゃくれている割には素直で隠し事の下手なこの少女の、微かにぎこちない笑顔に何人が気づいただろう。
「その人は余計だけど、でも、これは嬉しかった。ありがとう、ミコトさん」
「あー、わしらはまだ食事中ゆえ、控え室で待っておってくれんか。用件は後で聞こう」
咳払いをしてシドが割ってはいる。妻との熱い感動共有からようやく覚めたらしい。
「あ、なんなら僕たちも一緒にここで食事…いててて」
満面に笑みを湛えてまた図々しい申し出をし始めた兄の耳を力いっぱい引っ張ると、ミコトはにっこり笑って頭を下げた。
「ええ、そうさせていただきます。突然お騒がせして申し訳ありませんでした、大公さま」
そして渋るクジャを引きずるようにして部屋を出てゆく。
「痛い!痛いってばああ!」
「うるさいわね!行くわよ!とっとと歩いて!まったく恥ずかしいったら!」
あたり構わず兄弟げんかを晒しつつ廊下の向こうに消えてゆく二人の姿を、大公一家は思わず目で追ってしまった。
「へんな人たち」
ようやく訪れたいつもの平和な静寂の下、エーコが率直な感想を述べる。
その言葉を合図に三人は目を合わせ、いつしか微笑んでいた。
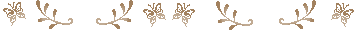
「エーコちゃん、ジタンのことが本当に好きなんだな」
「はあ?突然何?」
控え室に案内され、ふかふかのソファに腰を下ろすなりクジャは珍しく真面目な面持ちで洩らした。
「僕らの村に来なかったのも、多分それが原因じゃないかな」
「それって何よ」
「だから、失恋」
「はあ?」
ミコトからすると支離滅裂な論理展開である。ついていけない彼女は、真っ向から胡散臭そうにクジャを見る。
「ビビの命日がくる一月前にジタンとガーネットは結婚式をあげたろう?」
「ええ。そのときにエーコも招かれてて、ちゃんと式にも臨席していたわ。そしてちゃんと祝福してたわよ。ニコニコ笑って」
式には無論クジャも招待されたのだが、彼は出席しなかった。口でいろんなことを言っていても、彼は自分について誰よりも弁えている。だから彼がエーコを見るのは丸一年ぶりなのだ。
「笑ってるから平気ってわけじゃないよ。人は悲しいときにだって笑えるんだから。相手のことを思って」
「でも…病気だったってさっき本人言ってたでしょ」
あくまでミコトは懐疑的である。だがクジャは怯まなかった。
「さっきボクが跪いた時も、一瞬遠い目をしてたろう?気がついた?」
「ああ、そう言われれば」
手を引っ込めたときエーコの顔に去来したのは嫌悪感ではなく、むしろ寂寥感とも言うべき色だった。それをクジャは見逃さなかったのだ。
「とにかく誰かのことを強く想ってる目だった。でも思いが通じてる相手を想う時はあんな目をしない。だとしたら、彼女は片思いをしてるんだ。それも、絶対想いが適わない相手を。…となるとジタンしかいないじゃないか。しかも彼は結婚して、ガーネットの夫になった。挙句の果てにいちゃいちゃべたべただろう?あんな二人を見せ付けられるのは嫌だよね。失恋した身としては。だから一緒に黒魔導士の村に行くのを避けたんじゃないかな」
そこまで説明されてようやくミコトにも得心が行く。が、そのまま素直に同調するのも癪だった。
「…さすがに万年失恋してるだけのことはあるわね。その手の心理については詳しいわけよね」
錐でえぐるような皮肉にクジャはちょっとムッとする。
「…お前、いつも一言余計だよ」
「そう?それは失礼」
「まあ、いいけどさ。でも、僕の言うことは当たってると思うだろ?」
「それは…そうね。否定はしないわ」
不承不承彼女は肯いた。彼女はクジャよりはエーコに接する機会が多い。そしてたまにジタンやガーネットと手紙のやり取りをする。そんな中でそこはかとなくエーコの情報も得ていた。だからエーコ公女の周辺に縁談の匂いがないのも、彼女が未だ子どもよろしく走り回っているのも知っていた。シドたちに厳重に守られて、エーコはまだ恋愛そのものに縁がないのだと思っていたのだ。
だが、もしあの旅からずっとジタンのことを慕っていたのだとしたら――今回のエーコの行動の説明はつく。
「だったら、計画に乗ってくれよ」
出た。
「何の計画よ!いきなり!」
クジャのこの手の唐突な発言には慣れっこになっているはずのミコトだが、今回のように集中豪雨の如く濫発されては目が回りそうだ。
「エーコちゃんを失恋の痛手から立ち直らせてあげる企画だよ」
「また余計なこと…」
勘弁して、と言いたかった。こいつが企画することにろくなことはないのである。しかも、ミコトにはクジャの狙いなど手に取るようにわかるのだ。
「あわよくばエーコの気を引こうって魂胆でしょ」
「う…」
「ったくなに考えてるのよ。自分の年考えたことあるの?エーコより20も年上なのよ?信じられないわ。いつまで万年青年のつもりでいるのよ。もうおじさんなんだから。自覚しなさいよね、おじさん!」
「おばさんに言われたくないやい」
小さな声で反駁を試みるクジャ。
「何か言った?」
だがすかさずオドロオドロしい声で返されて、いっぺんで萎んでしまう。所詮彼はミコトには適わないのだ。
「いっ、いいえ、なんにもっ」
情けなさ半分悔しさ半分で喚くと、彼はシュンと肩を落とした。
「で…どんなことするつもりなのよ」
「へ?」
思いがけないミコトの言葉に、クジャは目をぱちくりさせる。
「エーコを立ち直らせるために、何をしようって企んでるか聞いてるの」
「ああ、それなら…荒療治が一番かなあ、って…」
「荒療治?」
「そう。本当は、黒魔導士の村に来て、ジタンとガーネットを見せ付けられるのが一番良かったと思うんだ。あれを見ればたいていの人間は諦めがつくだろう?」
見詰め合う二人。まさにheart to heartを体現したような二人を思い出して、ミコトはげっそりする。
「確かに、一晩で食傷気味にはなるかも」
「だから、ここに二人を呼ぶのさ。っていうか、二人だけじゃなくて、できたらエーコにつりあうくらいの男を集めてもらって、大舞踏会を開くのさ!煙幕としてね」
「…上手くいくかしら」
「さあ…だけど、きっかけにはなると思うよ」
「きっかけ…ねえ」
「うん」
自信をもって肯定するクジャを、ミコトは笑みを含んだ瞳で見つめた。クジャがこちらを向いていないことを確認したうえで。もしこんな顔ををしている時に目が合ったりしたら、恥ずかしくてたまらない。
かつてミコトの中に感情が芽生え始めるきっかけとなったのがジタンだった。そして雛鳥が刷り込まれるように、ジタンに対する信頼と情愛が心に生じた。それを恋愛感情と誤認するのに時間はかからず…彼女もまた、いわばジタンに失恋したのだ。
彼女の目を覚まさせてくれたのはほかならぬジタンと、そしてクジャだった。
どんなに時空を異にしていても、たった一人の女性を想い続けるジタンの姿に、自分が妹に過ぎないことを思い知らされた。そして二人と共に過ごすうちに、自分が感じていた思慕が「肉親の情愛」に極めて近いことに気がついたのだ。
ジタンはきっと自分にも優しい。親身になってくれるだろう。自分のために命も投げ出してくれるだろう。だけど、彼の心を埋められるのは自分ではないのだ。彼が自分の心に招き入れるのはこの世の中でたった一人なのだ。
そう、思った時、ミコトの中の何かが弾けた。すっと気持ちが落ちていって、そして悔しさ交じりではあったけれど、諦めがついたのだった。
エーコも、そうなのだろうか。クジャの言うように、あの少女もジタンを想い、そして悩んでいるのだろうか?
「まだ、本当の恋でも愛でもない。きっと、思慕なんだ…だから、きっと、目が覚める」
静かにそう呟くクジャの背中に、ミコトは額をくっつけた。
お節介だけど、でもあんたっていい人よね。そうしみじみと思うミコトの頭上で、クジャが熱のこもった台詞を付け加える。
「目が覚めた時に真っ先に目に入るのが、ボク。いわゆるインプリンティングってやつ?ここでばっちり印象付ければ、もう楽勝だね!」
嬉しそうな表情のまま後頭部を殴られて、彼はしばらく夢の中を彷徨う羽目になった。
|