|
まさかシドがうんと言おうとは、誰も想像だにしていなかった。
頼み込みに言った当のミコトでさえ、彼が快諾した時には仰天してしまったくらいだ。
むろん、例の大夜会の話である。
「あの子が浮かぬ顔をしているのがいたたまれぬのじゃ」
もともとお祭り騒ぎの好きな陽気な娘である。宴でも開けば気も晴れるだろうとシドは言った。
親の情とも言うべき感情にミコトはあまり接したことがない。だから、そう語りながら遠い目をして微笑むシドの表情の優しさに、思わず目が引きつけられる。
「どうしてそこまで…エーコのことを思えるのですか?」
つい、訊いてしまった。長いこと忘れていた昔の自分が不意に顔を出したような感触。
シドは鷹揚に微笑んだ。ミコトさえ受け止め、くるみこむような、慈愛といってもいい微笑だった。
「目の中に入れても痛くない、自慢の娘じゃからな」
「でも…」
「娘じゃよ」
ミコトの口吻で察したのか、シドは優しく制した。
「紛れもなくわしらの娘じゃ。あのこの中では整理はついておらんかもしれんが、わしらはそう思っておる。――そう難しい顔をするでない。お前さんがクジャやジタンに感じておる気持ちと同じじゃよ」
「血がつながっていないのに?」
「代わりに心がつながっておる。時間と真心を込めただけ、な」
そうしてその話題を切り上げるかのように、彼は懐から巾着を出して逆さに振って見せた。
「それにしても、ヒルダから貰うわしの小遣いでは、夜会開催はちと辛いかもしれんのぉ」
「まあ、まるで私が吝嗇のごうつく婆みたいなおっしゃりようですわね」
突然背後から起こった声に、シドがビクッと肩を震わせる。額に冷や汗を浮かべ、引きつった笑顔でシドは首をしきりに振った。
「いやいや、誰もそんなことは言ってはおらんぞ」
「あら、そうかしら。ま、よろしいですわ。たまにはファブール家でも夜会くらい催さねば、本当に吝嗇家に思われてしまいそうですものね」
「おお、ではわしのへそくりは使わなくてもいいと!?」
渡りに船、地獄に仏とばかりに顔を輝かせて、シドが歓声を上げる。
「とんでもない。足りない分を家計から出させていただくだけですわ」
しっかりものの良妻賢母…ヒルダは外見に似合わず庶民派であった。そして最後にさりげなくツボをつく事を忘れない。
「エーコのためなら、あなたと一緒に私も一肌脱ぎたいですもの」
うむ、とシドは唸るしかなかった。
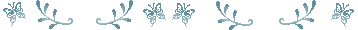
夜会は盛大に幕を開けた。
リンドブルムの主だった諸侯をはじめ、ジタンやガーネットももちろん招待してある。
ひとしきり招待客が軽やかなワルツにのって踊った後、主役のエーコが広間正面の大階段に姿を現した。
御年12のまだ幼さが残る容貌ではあるが、すでに美しさの片鱗が輝いている。将来は霧の大陸でも有名な美姫、ガーネット女王に並ぶ美貌になるであろうと誰もが思った。
少し伸びた髪をそのまま無造作に背中に垂らし、頭にある角を大きなレースの白いリボンでうまく隠している。共布の総レースのドレスの上に薄いオーガンジーのショールをまとった姿は、まるで泡の中から生まれ出た美の女神のようだった。
一瞬驚愕に彩られた沈黙に支配された広間は、すぐにどよめきで埋め尽くされた。それは主に男たちのため息で、パートナーの女性たちの眉宇が顰められたのは言うまでもない。
曲が終るごとにエーコの許にはダンスの申し込みが殺到するのだが、彼女は丁重に笑顔でお断り申し上げながら、さりげなくバルコニーに身を潜めた。
自分を心配してくれる両親の思いはありがたかった。でも、どうしても乗り切れない。どこか茶番劇のような気がするのだ。
夜風が気持ちいい。庭には夏の滴るような湿り気を含んだ空気が満ちている。ほんのりと、土の匂いと緑の匂いを含んだ風を頬に感じながら、エーコは浮かない顔で手すりに頬杖をついた。
部屋の大窓から漏れる明かりで、庭の緑が紺色の闇の中、ほのかに浮かび上がっている。大地のエネルギーを感じさせるが如く、四方八方に枝を伸ばす木々。あまり庭の手入れを行わないせいだ。シドに言わせれば「自然が一番」なのだ。そのせいでこの庭はすでに森林の一歩手前だった。
確かに、室内の薄っぺらい喧騒から逃れて一人ここに佇んでいると、この木々の生命力に体の奥から癒されていくような気がする。それは自然に根ざす召喚士としての血がなせる業なのかもしれないが。
「注目の的でモテモテのエーコ嬢が、なんでこんなところで不貞腐れてるんだい?」
目ざとく彼女を見つけた男が一人、仄暗い彼女のところへやってきた。振り向かなくても声と口調で誰かは簡単に想像がつく。
「なによ、こんなとこまで追っかけてきて、まだ言い寄るつもりなの?」
面白くなさそうな、どちらかと言えば物憂げなくちぶりだった。
いささか子どもらしくない台詞ではあるが、声にはまだ甘い幼さが残る。
振り向きもしない彼女の横に並び、彼女と同じポーズで頬杖をついて、クジャは軽く笑った。
「広間にいると、どうしてもキミの想い人が目に入る。しかも幸せそうな姿がね」
エーコは口角をきゅっと下げた。
「誰のことよ。勝手に決め付けないでくれる?」
少々気色ばむ。
笑いさざめく広間の声が時折音楽に乗ってここに流れてくる。人々のため息は今は広間の中央で踊る一組のカップルに向けられていた。
その名と同じ深紅のドレスを身にまとった女王。絹のような光沢の艶やかな黒髪が、パートナーのリードで軽やかに揺れる。
ゆったりと彼女をくるみ込むように巧みなリードを見せる相手は、すっきりとしたしなやかな体つきの青年である。珍しくきちんとした礼装に身を固め、愛しげに腕の中の女性を見下ろしている。その瞳をまっすぐに下から見上げて、己の全てを預けるような眼差しを向ける女性。
ほんのりと薄紅に染まった真珠の肌は、今にも光を放ちそうだ。
それはまるで天才画家の腕にかかった一幅の絵の如き光景であった。
匂い立つような美しさを呼び覚ましているのがパートナーの――夫の腕と眼差しであることは一目瞭然で、ゆえにその二人の強烈な結びつきが周囲を酔わせるのである。
が、片方に想いを寄せているものからすると、それはまことに面白くない光景でもあった。
「自分の嫁さん探しはどうしたのよ」
話題を変えようとエーコが矛先をクジャに向ける。
「ボクの審美眼に適う女性はこの中に二人しかいないんだ。残念なことに」
「じゃあ、その人と踊ってきたら?」
つっけんどんと無愛想を足して二乗したような冷ややかな態度で、つまらなそうにエーコが言い放つ。
「踊れないんだ」
「え?ダンス知らないの?」
初めて子どもらしい驚きを顔に乗せて、エーコがクジャの方を向いた。
その表情を見てクジャが嬉しそうに笑う。
「なに、その笑い。人を子どもだと思ってるんでしょ!失礼しちゃうわ。こう見えてもエーコはダンスはプロ級にうまいんだから!」
「それはよかった。だったら踊ってもらえないかな?」
「でもダンス知らないんでしょ?シロートとは踊れないのよ。エーコは上手すぎるから」
つんとそっぽを向くエーコ。
クジャはまた声をたてて笑った。
「ダンスを知らなくて踊れないんじゃなくて、僕が踊りたい相手は今踊れないってことだよ。ひとりは今広間で旦那と幸せそうに二人の世界を作ってるし、もう一人はここで不貞腐れてるから」
「なっ!なによぉ!まだエーコをからかう気!?」
「からかってなんかいないよ。心からお慕い申し上げております。エーコ様」
うやうやしく頭を垂れるクジャに、エーコは顔を真っ赤にして憤慨する。もっとも顔が赤いのは憤慨のせいだけではないようだが。
「ひ、人を馬鹿にして!申し訳ありませんけれど、わたくしには好きな人がおりますの!残念ながらあなたの出る幕はありませんことよ!」
いーっだ、と舌を思いっきり出して牽制する。だがクジャは一向に痛手をこうむった様子もなく、どこ吹く風といったていで体をエーコの方に向けた。
「ジタン・トライバルって言いたいんだろう?でも、残念ながらそれは永遠にキミの片思いで終っちゃうな」
「ほっといて頂戴!エーコは…エーコのナイトはジタンでなきゃ駄目なのだわ」
そっぽを向きながら――だが力なく彼女はそう付け足した。
呟きとともに視線はおのずと暗闇の彼方に向けられる。はるかな先だ。広間の明かりに紛れてちらほらとしか見えない、心もとない星の光のもっと向こう。
彼女の双眸からその視線をたどって、クジャは闇空を仰いだ。
「それは…きっと“彼”のことを知っている人じゃなきゃ駄目だからだろう?」
見透かしたように、呟く。エーコはぎょっとして一瞬振り返った。
「な、何言ってるの…」
「要するにエーコちゃんが拘ってるのは、ジタンじゃなくて、ビビなんだよね」
「また勝手なこと思い込んでる!」
つとめて平静を装い、冗談めかしてエーコが言う。だがクジャはごまかされなかった。
「ビビのことを忘れたくない。でも、忘れ去ってしまって平気でいるみんなが許せないんだ。特に鼻の下伸ばしてるジタンが嫌なんだろう?だから会いたくなくて僕らの村に来なかった。…おおかた、時期を外して一人でビビを偲ぼうとでも思ってたんじゃない?」
「ち、違うもん!」
むきになって否定すればするほど、それが図星であることを示すようなものだ。
「…そうだね。今ボクが言ったのは当て推量だ。真実はそうじゃない。多分君自身にもわかってない」
「…どういうこと?何を言ってるの?」
「キミはジタンが好きだった。その通りだ。今でも大好きだろう。だからガーネットと結婚してしまったのが面白くない。でも、キミはそんなことで捻くれて駄々をこねるような玉じゃない。表面はそう装ってるけど、ほんとは自分が許せないんだ」
「止めてよ。勝手なこと言わないで」
「忘れてしまったみたいに見えるみんなも嫌なら、時っていう魔法に絡めとられて記憶が風化していってしまってる自分も嫌なんだ。それを認めたくなくて、他に一生懸命理屈をくっつけてるんだ」
「止めてよ!ちゃんと覚えてるわ。全部、きっちり覚えてるわよ。あの旅も、ビビのことも、あの子の最後も、ちゃんと見届けたんだから。エーコは天才的に記憶力がいいの!カラカラの鈴みたいなノーミソのあんたとちがうんですからね!」
あまりの言われように、クジャも苦笑を隠せない。だが彼は舌鋒を収めようとはしなかった。
「エーコちゃん。ボクはあんまり人に助言できるような人間じゃないけど、これだけは言っとく。思い出を引きずっているうちはいい。でも、思い出に引きずられるようになっちゃ駄目だよ」
確かにエーコは利発な少女である。クジャの言わんとしていることを、すでに十分感じ取り始めていた。だからこそ言葉を返すことができずに、ただ唇を噛み締めることしかできなかった。
「時が過ぎるのは、いろんな物事を濾過して、必要なものだけを人の心の中に残していくからだとボクは思う。変わっていくことを恐れちゃ駄目だよ。――過去に囚われてしまう生き方はあんまりお勧めできないな」
そして彼は破顔した。文字通り、顔中で笑って見せたのだ。心底、明るく。
それから、静かに付け加えた。
「そんな生き方は、僕だけで十分だよ」
静かな、静かな響きが、紺色の闇に吸い込まれてゆく。
「クジャ…」
エーコはゆっくりと顔を上げた。かたわらで優しげに微笑んでいる青年の細められた瞳の奥に横たわる哀しみが、真綿のような少女の心に沁みこんでくる。
「変わって行ったって、ビビは絶対に責めないよ。大切なエーコがいつまでも自分に拘って、未来に目を向けられないでいる方が哀しいよ。それに――心配しなくたって、自分にとって大事な記憶は残っていくんだ。時は全てを押し流してしまうんじゃなくて、ちゃんと選別してくれるんだから」
「もう、いいよ」
エーコがそっと手を伸ばした。
「分かったから。おかげで、ふっきれたから。だから、もういいよ」
自分に向かって差し伸べられた小さな細い手を何と解釈したら良いのか分からず、クジャは当惑したようにぼんやりとその手を見つめて硬直している。
「握手」
「んあ?」
「だから、握手。ありがとうの」
「あ、ああ」
まだピンとこないまま、促されてその手を握る。
ほんのお義理程度の力しか込めない彼の手を力いっぱい握り返して、エーコはそのままきゅっと引っ張った。
引きずられそうになってクジャが慌てて踏みとどまると、エーコは不満そうに開いた方の手を腰に当ててふんぞり返った。
「何よ。あんたの理想の乙女がダンスの相手をしてあげようってのに、嫌なの?」
「い、いや、そんなことは…」
立場逆転。さっきまで説教を垂れていたクジャだが、今度はたじたじである。
「じゃあ、来なさいよ。あ、ただし、踊る前にその服だけは着替えてもらいますからね!」
「え?だってこれボクの一張羅なのになあ」
すこぶる残念そうにひらひらの腰布を広げてうなだれる。
「言ったら悪いと思って黙ってたけど」
「え?」
「あんたの服の趣味って最悪!」
う、っと一瞬クジャはたじろぐが、そこは舌先三寸男である。言われっぱなしで黙ってはいない。
「口が悪いのは分かってたけど、少しは綿にくるんだような言い方するもんだよ。ずけずけ言い過ぎるのはレディにあるまじき悪癖だと思うけどな」
「いいの。エーコはレディになんかならないもん」
「シド大公が悲しむよ。大切な一人娘が行かず後家になっちゃうかもしれない」
「レディじゃないエーコがいいって人を探すもん。それまで結婚なんかしないのだわ!」
つんとすまして言ってのける少女の頭を見下ろして、クジャは楽しげに相槌をうつ。
「それは残念」
うふふ、と嬉しそうにエーコは笑う。
「エーコが結婚を決意する頃にはクジャはおじさんもいいところだもんね」
「じゃあ今夜はかけがえのない一夜だね。なんと、未来のリンドブルム一の美女とダンスが踊れるんだから」
「そうよぉ!エーコが生まれて初めてお父さん以外の人と踊るダンスなんだもの。すごい記念だわよ」
そう言って、エーコは駆け出した。クジャの手を引いたまま。
闇に馴れた目にはまぶしすぎる広間の光の洪水が、瞬く間に二人の姿を包み込んだ。
彼らのたどってきた道も、これから歩いてゆく道も。
それぞれの人生を、そっと祝福するかのように。
|