|
第一幕 第一場
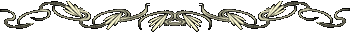
コーンウェール国は隣国フォロンツァ王国と仲が悪い。
些細ないさかいと行き違いが重なって、フォロンツァが宣戦を布告。国境に軍を配した。
コーンウェールの王、オーラフは、事態を重く見て宗主国レアンに使者を送ることにした。
レアンの目を盗んで国力を蓄えてきたフォロンツァ王国とコーンウェールでは兵力の差は歴然。レアンの援軍なしでは敗北は必至だった。
だが帝国レアンに行くにはフォロンツァ王国の陣地を横切らなければならない。この危険な任務に志願するものなどいないのではないかと思われた。そのとき、一人の勇気ある騎士が名乗りを上げた。
クリストフ・ジャンニ。
黒い甲冑に身を包み、黒毛の馬にまたがって戦場を駆け抜ける姿は黒獅子と異名をとった。勇猛果敢な無敵の剣士である。
その後に続いてクリストフの盟友バルテロー、デイビス両名も名乗りでる。
オーラフはいたく喜び、クリストフの手をとって誓った。
『見事使命を果たしこの地にたどり着いた暁には、そなたにわが娘をとらせよう。』
一人娘の王女リデルは若く美しかった。バラ色の頬を染めて、父王の傍らで小さく膝を折った。
彼女は幼い頃からこの勇敢な青年に恋をしていたのである。
クリストフは跪き、王オーラフに奏上する。
『もったいないお言葉、誠にかたじけのう存じます。しかし私は褒美のためではなく、コーンウェールのために命を尽くす所存でございます。』
それをきいたリデルの瞳がふと翳る。
だがオーラフ王は満悦し、鷹揚に肯くと騎士の手をとって立ち上がらせた。
『良い心がけである、騎士クリストフよ。そなたの心根はジャンニ家の誉れとして末代まで語り継がれよう。』
そして王は彼らに告げた。『では行くが良い。幸運の神獣がそなたたちの上にあらんことを』

|
![]()