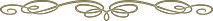
第二幕
コーンウェールの若き騎士が厚い囲みを破って帝国レアンに到着したとの噂は、瞬く間にフォロンツァ全土に広がった。
歯噛みして悔しがるくにたみをよそに、ソフィアはほっと安堵のため息をつくのだった。
レアンの援軍がたつ前に、フォロンツァは降伏し、コーンウェールと和平を結んだ。
やるべきことを果たし、任務を終えたクリストフは、一路フォロンツァの辺境の村に馬を走らせる。
彼の身を案じ、祈りを捧げ続けた乙女は、村の外れで騎士と再会した。
黒毛の愛馬から降り、クリストフはゆっくりと娘に近づく。
ソフィアは喜びに震え、大きな瞳に涙を湛えて丈高い青年を見つめ続ける。
そして騎士は娘の前に跪き、礼を尽くして花を捧げた。
『この花の言葉と同じ永遠の愛を、私はそなたに捧げよう。』
かくして花の如き肢体は逞しき腕に収められ、二人は頬を寄せ変わらぬ愛を誓い合うのだった。
だが相愛する若き二人を引き裂くさだめは、間をおかずにやってきた。
割譲されたソフィアの村はいまやコーンウェールの所領となった。そこに王宮からの使者が到着したのである。この村にとどまったままの英雄を都に凱旋させるべく、王がよこした遣いだった。
都にはクリストフの年老いた両親がおり、彼らもまた、息子の帰還を心待ちにしている。
一旦は帰らねばなるまいと心を決めた騎士は、村娘の手を包み、夕づつの下、別れを告げた。
ひとたびこの地に戻ってくるとの約定を果たしたように、ふたたびの約束も必ず果たすと、騎士は言葉すくなに村娘を抱きしめる。
ソフィアは涙を見せることなく、気丈に笑って騎士を見送った。
別れの予感を、吹く風に零しながら。
ジタンは、歌を歌わない。
この戯曲には数箇所歌が挿入される。その殆どが村娘ソフィアが騎士クリストフを想って歌うものだが、一曲だけクリストフ自身が歌う箇所があるのだ。
なのにその箇所をジタンは台詞で流してしまった。
どうして歌わないの?と尋ねるガーネットに、ジタンは素っ気無く歌いたくないからと答えた。
「大体さ、どうして普段どおりの会話をしながらいきなり歌いだすんだ?あれって変だよな」
「そうかしら?言葉だけよりずっと人の心が表現できると思うわ。第一、印象に残るわ」
「俺の役なんて印象に残らなくていいの。お前が主役なんだから」
いつものように口当たりの良い言葉でうまく煙に巻いてしまおうとするジタン。だがガーネットも心得たもので、そんなおためごかしの懐柔作戦には簡単に乗りはしない。
「…私は、あなたの歌が聞いてみたかったな」
寂しげに呟かれてジタンは言葉に窮する。
そこへ休憩を終えたタンタラスの一団が戻ってきた。
ジタンが歌ってくれないとこぼすガーネットに、面々は顔を見合わせ苦笑いする。
「残念だけど、俺たちも聞いたことねえんだ」
「舞台の上…ってゆーか、人前でうたわへんもん」
「恥ずかしがり屋さんずら〜」
「だから諦めるしかないっす。俺が思うに、ジタンさんは歌があんまり得意じゃないんじゃないかと…」
「そうずら」
「おっ、お前ら…」
「俺もそう思う。だからさ、残念だけど、あんたも我慢してやってくれよ」
「せやせや、からしソースも腐るような歌なんて聞かせられたらたまらんしな」
「それは言いすぎっす。スープは腐るかもしれないっすけど、ソースは大丈夫っすよ…多分」
「結局腐るのは同じずら」
「要するにジタンが歌うのはタンタラスのイメージダウンやねん」
「お前ら!!!いい加減にしろって!」
ようやくジタンは会話に割って入れた。とにかく彼らが喋り始めたら止まらない。雪山の直滑降みたいなものだ。隙を見つけるのさえ一苦労で、ジタンは額に汗をかいて、肩を泳がせている。
「あのなあ、俺は単に歌なんてうざったくてやってらんねえだけなの。お前らの魂胆はわかってんだ。そうやって人を挑発して歌わせようってんだろ。でも俺はその手にはのらねえ!絶対歌わないからな、ぜったい!」
腕を組んでつんとそっぽを向くジタンを、困ったようにガーネットは見つめた。
細いため息をついて、ぽんぽんと彼の背中を叩く。
「わかったわ。無理は言わないわ。だからせめて、私の相手役として舞台に立って?――だって、私にとっては最初で最後の大舞台なんですもの」
そう言って彼女は俯いた。
相手はあなたしか考えられないもの。
ジタンにしか聞こえないような小さなささやきを付け加えながら。
その呟きのどこか寂しげな響きが、胸に突き刺さったような気がして、ジタンはまたもや言葉に詰まる。
「・・・分かってるよ。それは大丈夫だって」
それでも彼の返答は素っ気無かった。
ガーネットがリンドブルムに来てからもう5日たっている。
なのにジタンは稽古場でしかガーネットと顔を合わせようとしないし、相変わらずあまり口もきかない。
ガーネットはできるならジタンともっと話したいし、もっと触れ合いたかった。でもジタンの態度は一向に軟化せず、結局現状でそれが可能なのは稽古の最中しかなかった。
騎士クリストフと村娘ソフィアとしての抱擁。
「じゃ、第二幕からいくぞ!」
村娘の許に騎士が帰ってくるこの場面で初めてその「抱擁」シーンが出てくる。バクーの一声に、ガーネットの胸は我知らず高鳴った。
読み合わせはとうに終了し、すでに立ち稽古に入っている。
全部台詞が入ってしまっているガーネットは、台本も持たずに中央に立った。
一方のジタンももう台本を離している。この男の凄まじいほどの記憶力は周知のことだ。いまさら誰も驚きはしない。
「ソフィア」
ジタンのよく響く声がそこを一瞬にして舞台の場に変える。
「遅くなってすまなかった」
台本にある通り、ガーネットはゆっくりと振り返った。
彼女の演技もなかなかのものだ。素人の域は脱している。…むろん、馴れていないせいもあって、若干のわざとらしさも残ってはいるが。
「クリストフ様」
鈴を転がしたような可憐な声音だ。ジタンはちょっと苦しそうに眉を顰めた。
「駄目だ駄目だ!!なんだその表情は!再会の喜びに震えるクリストフがそんな顔をするか!馬鹿者!」
すかさずバクーのチェックがはいる。
「…わかってるよ」
むすっとしてジタンは腰に手を当て、小さくため息をもらして床に視線を落とした。
ガーネットの声。思いのたけを込めて名を呼ぶときのあの可憐な声に昔から彼は弱いのだ。胸を鷲掴みにされるような感じになる。もしくはかきむしられるような。思わず、衝動的に抱きしめてしまいたくなってしまう。堪えに堪えて、抑えている気持ちが噴き出しそうだった。
それを我慢するものだから、あんな苦しげな表情になってしまうのだ。
ジタンはもう一度だけ深く息を吸って、吐いた。
「じゃ、そっちの台詞から頼むわ」
軽く笑って、彼はおどけた調子で言った。
ガーネットは肯いて、ジタンの役名を呼ぶ。
「クリストフ様」
大股でガーネットに近づくジタン。彼女の目の前まで来ると、彼は跪いた。そうして彼女の手をとり、花を捧げる。
「この花の言葉と同じ永遠の愛を、私はそなたに捧げよう」
「クリストフ様…。いけません、私は賤しい村娘です。あなた様のような高貴なお方から、このようなお心を頂けるような者ではありません。どうか、どうかおやめになってください」
ガーネットは慌てて手を引き、ジタンの前にぬかづいた。
「人を――人を思う心に貴賎はないのだ。花の…娘よ」
ジタンはそっと手を伸ばし、ガーネットの頬に触れた。
叩頭していたガーネットの髪がかすかに震える。
「顔を上げよ」
騎士の口調は微妙な変化を遂げている。気付いていながら誰も止めようとはしない。むしろ引き込まれるように固唾を飲んで見守っている。
「二度と離れぬ。二度と離さぬ。とこしなえに私はそなたとともにある」
面を上げたガーネットの白い頬が濡れている。
村娘ソフィアに彼女の心も重なっているのだ。ジタンがクリストフに己を重ねてしまっているように。
「そなたの想いを聞かせてくれ。そなたが私を拒むなら、無理強いしようとは思わぬ」
すっくと、騎士は立ち上がった。
土埃に薄汚れたマントが風にたなびく――見守るタンタラスの面々の目に、一瞬そんな幻影がかすめる。
じっと娘を見つめ、答えを待つ騎士。だが娘は唇を固く噛み締め、俯いたまま土くれに爪を食い込ませた。細い肩を震わせながら。
悲痛な面持ちでジタンは踵を返し、ガーネットに背を向けた。
その背を見た途端、こらえきれないように娘が叫んだ。
「私は!」
ジタンが立ち止まる。凍りついたように。
「私はあなた様をお慕い申し上げております。クリストフ様…!」
あなたをお慕いしています。――ジタン!
台詞の奥に秘められた彼女の想いは、強く強くジタンの背中を突き破る。
彼はおもむろに振り返り、それから足早にガーネットの許に戻ってきた。そして力任せに彼女の腕を掴んで立ち上がらせ、次の瞬間乱暴なくらいに抱きしめた。
「愛している」
耳元で渾身の気持ちを込めて一言呟くのが精一杯だった。
ガーネットの体は痛いくらいにジタンの胸に押し付けられて身動きが取れない。なのに彼女は更に彼の胸に顔を埋めようとする。ジタンのぬくもり。ジタンの・・・匂いがする。このまま、離れたくなかった。
固く固く抱きしめて、ジタンはガーネットの髪に顔を埋める。
離したくない。この柔らかな華奢な体を、ずっと腕の中に囲っておきたかった。
それはクリストフの気持ちではなく、溢れてしまった自分の想いだった。
「なんやーっ!!いつまで抱きおうてんねん!うちが出られへんやんかあーっ!!」
あんまり二人の抱擁シーンが長すぎて、痺れを切らしたルビイが怒鳴る。
その声が、二人の意識を現実に引き戻した。
「あっ」
「あ…わりい」
ばっと体を離して、二人は一様に顔を赤らめた。
「ったく、気持ちが篭ってんのはええけど、こめすぎや、っちゅうの。周りのもんはええ迷惑や」
台本でぱたぱた仰ぎつつ、おばはんのような物言いでルビイが文句を垂れる。
「とか言いながらうっとり見惚れてたのはどこのどいつだよ」
ぼそっと後ろで突っ込むブランク。
「何か言うた?」
鋭い目つきで振り返るルビイの視線に、ブランクは慌てて目を逸らしながらしらばっくれる。
「いいえ〜。言いませんよ〜」
「でも、いい感じっすよ」
「まるで本当の恋人同士みたいずら〜」
残る二人の朴訥かつ微妙にずれた感想を遮って、バクーが立ち上がった。
「今日はここまでにしといてやろう。10日間の稽古のちょうど中日だ。午後はお前らにやる。自由に過ごせ」
ひゅ〜、とブランクが口笛を吹いた。
自分の出番の寸前で稽古を止められたルビイは憤然としかかったが、いつのまにか横に来ていたブランクに腕を掴まれて「粋な計らいだな?」とウインクされてはそれ以上怒りようがなかった。
きょとんとしているマーカスとシナは?マークを振りまきながらとりあえず部屋を出て行き、後に残されたジタンとガーネットは、しばらくの間身動きがとれずに呆然と佇んでいた。
真っ先に部屋を後にしていたバクーは、通りに面した階段を下りながら苦虫を噛み潰したような顔で首を鳴らしていた。
「ったく、手間のかかる野郎だ。・・・ここまでしてやらにゃあならんとは!…せっかくのお膳立てを無にするんじゃねえぞ」
さてその呟きが届くかどうか――。
誰もいなくなった部屋の中では。
話しかけも出来ず、さりとてその場から先に立ち去ることも出来ず、ぎこちない空気の中、ジタンとガーネットは反対の方向を向いたまま立ちすくんでいたのだった。


