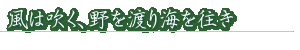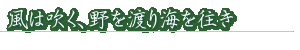|
1、プロローグに代えて〜レオン
レオンハルト=アーシス=スタイナー、というのが彼の本名らしい。
フルネームで呼ばれたのは生れ落ちてこの方、誕生の祝福を受けた時だけなので、彼の正式名を知る人間はまことに少ない。その少ない人間の中に、アレクサンドリア王家の王子と王女が含まれるのだから、その素性は推して知るべしである。
彼の両親はあの「伝説」のガイア戦争を戦い抜いた英雄なのだ。
吟遊詩人や劇作家たちの手によってかなり脚色されて広まったために、戦いの真の姿は覆い隠されてしまったけれど、二人が人口に膾炙するほどの傑物であることは間違いない。その父の名をアデルバート=スタイナー、母の名をベアトリクスという。
レオンハルトが戴いているアーシスという名称はベアトリクスの祖父の名で、彼女がスタイナー家に嫁ぐ時に、この名だけは絶対に受け継がせるようにと申し渡されたいわく付の代物だった。
この祖父というのがまたアレクサンドリアでも有名な英雄で、先のリンドブルム戦役から延々と続いたいわゆる百年戦争の終盤、私兵団を率い、メリダ平原において敵国ブルメシアを撃退せしめた、という伝説を残しているくらいのツワモノなのだ。
つまりは化け物じみた怪力の闘士とか稀代の名剣士とか、人間離れした逸話に事欠かぬ家系の末端に生を受けてしまったのがこのレオンハルト=アーシス=スタイナー、なのである。
これだけ有名な家系である。小さな頃から色眼鏡で見られるのは当たり前、あちこちで嫉妬や妬みややっかみに晒されて、物心つく頃には見事アンニュイでシニカルな人格ができあがっていた。
だから当然というべきか、彼もその他大勢の貴族の子弟と同じく私塾に通って勉学に勤しんでいたわけだが、どうもその性格が災いして親友というものができなかった。無論、親の七光りにふらふらと引き寄せられてゴマをすろうとする輩もいないではなかったが、当のレオンがそういう手合いを鼻にもひっかけなかったのだ。
従って私塾でも彼はたいてい手持ち無沙汰で、机についている間は居眠りを決め込み、休みの時間には学友を泣かして回っていた。
もっとも、彼の名誉のために一言だけ付け加えるなら、「泣かして回っていた」のにも理由はあるのである。名ばかりの学友連中は、高い禄をはむスタイナー家の御曹司を憎々しく思っていたから、結託して彼をよく仲間はずれにした。えげつないやり口で不意を襲って湖に突き落としたり、泥を投げつけることもあった。
むきになって怒るのも馬鹿らしかったのでレオンはおおかた無視していたのだが、「反撃が返ってこない」と踏んだ彼らはかさにかかって彼をからかい始めた。これにはさすがにレオンも閉口した。そこで、小うるさい奴らから血祭りに上げていくことにしたのである。
おかげで二三日も経たないうちに学友どもの調謔は影を潜めた。
先んずれば人を制す。
兵法ってのは結構的を射ているものなのだと、齢十にして実感した瞬間であった。
そんな刺激的な少年時代を送っていた彼にも一つの転機が訪れる。
十五になったばかりのある春のことだ。
父のアデルバート=スタイナーについて城に上がった彼は、不審な賊を見つけて直ちに捕らえようとした。腕には自信があった。何しろ、名うての剣士である母親は言うに及ばず、稀代の名騎士と謳われる父、アデルバートからさえ3本に1本は取れるのだ。同じ年頃で彼に適う者は一人もいない。自分の技量に溺れるのも致し方ないところである。
だが、現実はそう甘くはなかった。あっという間に彼は返り討ちにあってしまったのだ。
腰に短刀を佩いているにも関わらず、男はその短刀を抜かなかった。素手で大剣を振りかざす自分と対し、簡単に組み伏せたのである。慌てず、騒がず、まるで日常の所作の続きのように。
金色の髪に金色の尻尾をもったその男は、地面に押さえつけた少年を澄んだ碧い目で見下ろすと、にやりと人の悪そうな笑みを浮かべて手を放した。
解放されたレオンは咳き込みながら半身を起こし、まじまじと相手をみつめて、それが女王陛下の夫君であることに気付いた。
どちらかと言えば口達者なレオンだったが、このときばかりは敗れたショックと相手の人物の二重打撃を受けて固まってしまった。挙句、ジタン陛下から「まだまだだな」と揶揄されたのである。これまで積み上げてきた自信が、それはもう見事にがらがらと音を立てて崩れ落ちていった。
ジタンその人と直接対面したのはそれが初めてである。
とにかく強くて人が悪い、という印象がレオンの中に刷り込まれてしまうのだが、それは横に置いておくとして、要するにこの事件がきっかけとなり、彼はジタンの息子、王子ルシアスの剣の手ほどきを任されることになったのだった。
ルシアスは11になったばかりの素直な少年だった。人を疑うことも詰ることも知らぬ優しい男の子で、さしものレオンも情にほだされそうになることが何度もあったくらいだ。が、もともと情の強い男のこと、鍛える手を加減することなど全くなかった。それがまた女王陛下と夫君にはいたくお気に召したらしい。よく彼を城に招いては、まるでルシアスの兄であるかのように接してくれた。
永らく友というものを作らず、その身の内に少しばかり孤独を抱えて育ってきたレオンには、これはかなり応えた。もともと根は父親譲りの真っ直ぐな気性である。この王家のためなら自分の命さえ捧げようと思い込むまでに、さして時間はかからなかった。
そうこうするうちに一年が経ち、ある日城下に出かけたルシアスが暴漢に襲われる事件が起こった。側につき従っていたレオンの手によりすぐさま暴漢は取り押さえられ、ことなきを得たのではあるが、ルシアスは左手に浅い傷を負ってしまった。
もちろんそれは手の甲にうっすらと血が滲む程度の傷でたいしたことはなかったのだが、レオンはひどく自分を責めた。
ジタン陛下の「まだまだだな」がずっと耳に残っていた上にこの事件である。
王家の警護を全うするつもりなら、こんな腕ではどうにもならないのだ。レオンは痛感し、そして一大決心をする。
修行に出よう。
俗に言う武者修行の旅に出るしかないと思ったのだ。
大人になってから思い出せば顔から火が出そうになるのだろうが、この頃のレオンにとっては正直アレクサンドリアの尖塔から飛び降りるくらいの決心だった。
しかもすごいことに、出立を決めたその日、彼は湖の岸辺に仁王立ちになって拳を固く握り締め、湖面の彼方を渡ってゆく風と雲に向かって更なる飛躍を誓ったのだ。
シニカルな表情の裏に熱い血潮がたぎる!
レオンハルト=アーシス=スタイナー…やはり血は争えないものだと周囲に知らしめた、16歳の夏であった。
さて、さぞかし周囲は猛烈に反対するだろうと思いきや、何のことはない皆至極あっさりと彼の申し出を容認した。やや拍子抜けしたものの、一旦言い出したら後には引けないし引く気もない。彼は即日旅の用意を始めた。
あくる朝早く、彼はアレクサンドリアの街を出た。
未練と分かっていながら最後に一度だけ背後を振り返った目に、塔の上から懸命に手を振る少年の姿が飛び込んでくる。
大々的に壮行会でも開こうものなら、もし中途で挫折して帰ってきたときに身の置き場がなかろうと、さりげなく普通どおりに彼を見送った大人たちの思惑とは別に、己の情に忠実な幼い子どもの精一杯の惜別だった。
レオンはそれを目と胸に刻みつけ、そして腰に佩いた見事な大剣の柄を握りしめた。
前夜父アデルバートが黙って自分に渡してくれた剣。
それはエクスカリバーと呼ばれる、伝説の名剣だった。
|